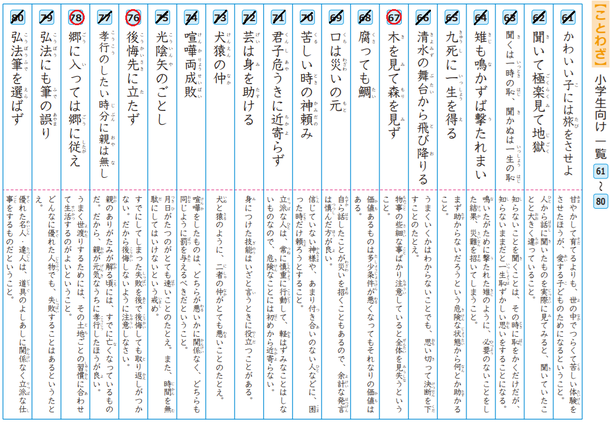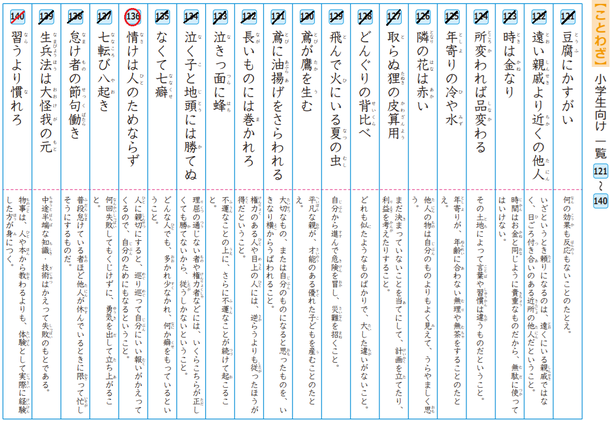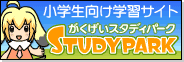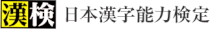【推薦入試対策 小論文・作文2】
〔ことわざ〕
〔意味/理由/意義〕
「意味」とは?
「意味」は、言葉や行動によってそのようになる必要性のことです。
例えば、遅刻をするという行動を取る場合、その必要性を求められた場合、これは「意味」になり、明確に遅刻という行動を示す必要性を問われます。
この時に必要ではないといえば、遅刻という行為は「意味が無い」となるのです。
よって「意味」は、そうなる必要性のことです。
「理由」とは?
「理由」は、物事の結果がそうなる必要性に着目しています。
いわゆる結果論のみを追究しているのが「理由」で例えば、「遅刻をした理由」という言葉は結果論で遅刻をしたわけは何かを聞いており、これも、「遅刻をした理由はない」といえば、結果を離さずにことを終えることができるのですが対象の評価はわけもなく遅刻をしたということで評判は大きく下がります。
「意義」とは
「意義」は、行動を起こすことによって得られる物のことで行動すれば何を得られるかが明確でないと「意義が無い」となり行動を起こす必要性が無いということです。
逆を返せば、「意義」は見返りがあるが故行動するともとれ、「存在意義」という言葉であれば、その場所にいると何か見返りがあるが故、その場所にいるというだけです。
よって「存在意義は無い」と言われると相手側が激怒するのは、見返りが無いのにも関わらず自分を呼んだが故相手は激怒するわけです。
「意味」と「理由」と「意義」の違い
「意味」と「理由」と「意義」の違いですが、見返りを求めるという意味で使用する「意義」だけはまず見返りがある前提なので異なる意味になります。
よって比較すべきは、「意味」と「理由」で「意味」はなぜそうなるのかを重要とします。
これには見返りを求めていませんのでなぜそうなるかだけを一番に考えるのが意味になります。
しかし、「理由」は結果論が重要でこれも見返りを求める必要性が無い結果論を指します。
よって「意義」だけが見返りを渇望し、見返りが無い場合においては、見返りがないが故激怒されるというわけです。
まとめ
「意義」については、見返りが需要で、例えば、「働く意義」は、見返りにお給料がもらえますので意義があると言えますが、それと同時に少ない「給料で働く意義」となれば、働くことに見返りを感じるかどうかは別問題です。
一方「意味」においては、見返りというより何故そう行動するのが重要で、「働く意味」であれば、お金をもらうためという目的があります。
そして「理由」は何故そう行動するかという結果論で、「働く理由」とすれば借金があるから返済のために働くや、家族を養うためという結果論からどうあるかを示すわけです。
この3者は難しく考えてしまいそうだと感じた場合、身近なことに置き換えるとその言葉の真意が分かります。
例えば、上記に記載した働くという言葉であれば、「働く意味」や「働く理由」に「働く意義」という言葉に置き換えると身近なことであればその真意が分かります。
〔ボランティア〕
「ボランティア」とは?
「ボランティア」とは、「志願兵」あるいは「自ら進んでことに当たる」などという意味をもっている英単語の「volunteer」を語源とする言葉です。
日本語で使われる場合は本来の英語の意味とは異なり、「無償労働」や「社会奉仕活動」などという意味合いで用いられており、元々英語の「volunteer」には含まれていない「ただ(無償)で手伝う」などというニュアンスが強めの表現として使用されています。
「奉仕」とは?
「奉仕」とは、「自らの利益を考えずに他人のために力を尽くす」さまや「お客さんのために商品やサービスなどを特別に安く販売する」様子などを示す言葉です。
「見返りをまったく求めずに助力する」もしくは「自分の負担や手間などを考えずに力を尽くす」などというニュアンスで用いられており、「献身(けんしん)」ないし「奉公」などという語句と同じようなニュアンスで用いられています。
「ボランティア」と「奉仕」の違い
「ボランティア」と「奉仕」は、どちらの言葉も「相手のために尽くす」などという意味合いで使われています。
先述のとおり日本語の「ボランティア」は「自発的に自分の手を貸す」というニュアンスを含む表現ですが、「奉仕」はどちらかというと「半強制的に活動に参加して自分の手を貸す」というニュアンスを含んでいますので、双方の語句は異なっている意味をもつ表現であると言えます。
「ボランティア」の例文
・『ここ2年ほどビーチクリーンのボランティア活動を続けています』
・『介護施設におけるボランティア職員が不足しています』
「奉仕」の例文
・『来週の奉仕活動はどこで行われる予定でしょうか』
・『お客さま奉仕セールは明日から開始する予定です』
まとめ
「ボランティア」と「奉仕」は、どちらの言葉も「相手のために活動する」などという意味合いで使われています。
使用する際にはそれぞれの語句がもっている微妙なニュアンスの違いに注意をしながら上手に使い分けるようにしましょう。
〔教育/躾〕
「教育」とは?
「教育」は「きょういく」と読み、意味は以下の通りです。
1つ目は「望ましい人間性を形成する為に、知識や技能を身に付けさせたり、自己啓発させたりして、能力を伸ばしていく試み」「学校の課程により身に付けた成果」という意味です。
「教育」の言葉の使い方
「教育」は名詞として「教育する・した」「教育を受ける・受けた」「学校教育」などと使われます。
基本的に「社会的な組織により作られた課程で学び、能力を伸ばしていくこと」に使われる言葉です。
「躾」とは?
「躾」は「しつけ」と読みます。
意味は「礼儀作法が身に付く様に、人に教え込むこと」です。
人に対する礼儀や正しいやり方など、人間関係を円滑に進める為に必要な知識やルールなどを教えることを表します。
「躾」の言葉の使い方
「躾」は「躾する・した」「躾が良い・悪い」「躾される・された」などと使われます。
「躾」という漢字は国字で、国字とは「漢字の字体にならって日本で作られた文字」で、「躾」の場合、「身を美しくする」という意味から作られた漢字です。
語源は仏教用語の「じっけ(習気)」という言葉で、「習慣性」という意味です。
ここから転じて「仕付け」「躾」として使われる様になり、「馴れさせる」という意味になりました。
基本的に、「社会的な礼儀作法を教えること」に使われる言葉です。
「教育」と「躾」の違い
「教育」は「社会的な組織により作られた課程で学び、能力を伸ばしていくこと」という意味です。
「躾」は「社会的な礼儀作法を教えること」という意味です。
「教育」の例文
「教育」の例文は以下の通りです。
・『すべての子供に学校教育を受けさせるべきだ』
・『教育現場では教師の過重労働が問題になっている』
・『新人教育の一環として自衛隊に入隊させる』
「躾」の例文
「躾」の例文は以下の通りです。
・『彼女の家は躾が厳しい』
・『躾の良いお嬢さまと付き合う』
・『親は子供の躾に苦労する』
〔普遍/不変〕
「普遍」とは?
広範囲に万遍なく行き渡る様を表すのが「普遍」【ふへん】です。
一つに偏ることなく、すべてに行き渡る様子を表すときに使われています。
たいていは「普遍的」といったように「的」を付けて使われている言葉です。
使い方としては、「どの国にも普遍的な魅力がある」といえば、その土地には他国に自慢できる面白さや美しい自然があるといった意味で使われています。
「不変」とは?
その様が一向に変化しない様を表すのが「不変」【ふへん】といいます。
状況が変わろうが簡単には変化せず、決まった状態が続くといった意味で使われている言葉です。
使い方としては、「常に不変的なものに強く惹かれる」といえば、以前と変わらない状況を好む人の気持ちを表します。
よく使われているのが変わらない景色や味といったもので、「不変的な魚の味に惹かれる」と自分の感情を伝える言葉です。
「普遍」と「不変」の違い
「普遍」と「不変」の違いを、分かりやすく解説します。
どこにも同じように行き渡る公平な魅力があり、偏らない美しさや事実といったものが万遍なくあるといった意味として使われています。
例えば、子供の可愛さは「普遍的な事実だ」と、どの国でも同じように感じられるものと受け止められているのです。
もう一方の「不変」は、いつまでも変わらぬ味、景色、造形といったものに心が奪われる感情を表します。
「普遍」の例文
・『子供が欲しいという欲求は、生き物が持つ普遍的な望みである』
・『美味しい物が食べたいと思うのは、誰もが持つ普遍的な欲求だ』
「不変」の例文
・『旅館の窓から見える不変的な庭園の景色に心が癒される』
・『熱川で食べた不変的な金目鯛の味が忘れられない』
〔間違える/誤る〕
「間違える」とは?
正しくない判断して実行することを「間違える」【まちがえる】といいます。
このような行動が起きる原因としては、事前に行き先の場所を認知していない、確かめた情報自体に誤りがあったとき、本来とは異なった行為する場合もあるわけです。
このように、物事に取り掛かるとき正しい行動ができない自分の誤った行為を指します。
「誤る」とは?
正しくない判断する失敗を「誤る」【あやまる】といいます。
使い方としては、「機械の操作を誤る」といって、正しくないボタンを押してしまった自分の誤った行為を指すわけです。
また、「誤った認識」といえば、正しく認知できなかった自分の愚かな状態を表します。
このように、やりそこなったり、正しくない方へと自らが行動を指す言葉です。
「間違える」と「誤る」の違い
ここでは「間違える」と「誤る」の違いを、分かりやすく解説します。
ドアを開けようとしたとき、鍵穴に別の鍵を入れるといった勘違いと似た行為することを「間違える」といいます。
他のことを考えていたり、お酒が入ると人は正しい判断が出来なくなり、勘違いしたり、本来やるべき行動が出来なくなるのです。
もう一方の「誤り」は正しい判断ができず、思い違いや違う行動した挙句、失敗する状態になるといった違いがあります。
「間違える」の例文
・『電話で話しながら歩いていると、乗るべきバス停を間違えた』
・『昼食に食べるものを考えていると、かける電話番号を間違えた』
「誤る」の例文
・『眠気に襲われて操作を誤り、本来は押さないボタンを押してしまった』
・『外にいる鳥に気をとられて、記入する名前を誤った』
〔努める/図る/計る〕
「努める」とは?
努める」とは努力するという意味の言葉です。
業績向上に「努める」というように仕事などで長期的に頑張るという意味で使われることもあれば、平静を保つよう「努める」というように短期的に何かを我慢するような使い方もされます。
仕事をする意味での「つとめる」という言葉は他にもありますが、「努める」はただ仕事をこなすだけではなく通常より精を出す、無理があっても我慢して耐えるという頑張りを強調する言葉です。
「図る」とは?
「図る」とは何かを実現しようと企てることやそうしようとすることです。
どうすれば実現できるかと考えて実現のために打てる手を打つという意味があるので、転じて実現のために努力するという意味で使われることもあります。
ただし言葉としては努力するという意味は薄く、目的のために考えることや工夫するという意味が強い言葉です。
長期的な計画を考えることも指しますが、なんらかの行動を起こすという短絡的な行動についても使われます。
「努める」と「図る」の違い
「努める」と「図る」の違いを、分かりやすく解説します。
なにかのために努力したり我慢することが「努める」で、何かを実現しようと企てたり目的のために行動しようとすることが「図る」です。
「努める」はなにかのために頑張ることと言い換えられますが、「図る」は努力するという意味合いで使われることはあっても言葉自体には努力するという意味はありません。
まとめ
「図る」は実現のために考えたり工夫することという意味が実現のために努力することと捉えられる事があり、それが努力するという意味の「努める」と類似した言葉として扱われる原因です。
ですが「努める」は努力するという要素を強調している言葉であるのに対し、「図る」の本来の意味は努力するではなく企てるや工夫するということなので、全く別の言葉と思っておくべきでしょう。
〔履き違える/勘違いする〕
「履き違える」とは?
「履き違える」は「はきちがえる」と読み、意味は以下の通りです。
1つ目は「他人の履物を間違えて履くこと」という元の意味です。
2つ目は「履物を左右間違えたり、左右で違うものを履くこと」という意味です。
3つ目は転じて「あることの意味を、別のものと取り違えること」という意味です。
「履き違える」の言葉の使い方
「履き違える」は、「履き+違える」で成り立っている語です。
「履き」は動詞「履く」の連用形で「履物を足につける」という意味、「違える」は「誤る・間違える」という意味、「履き違える」で「履物を間違って足につけること」という意味になり、転じて「あることの意味を、別のものと間違えること」という意味の慣用句として使われる様になりました。
「勘違いする」とは?
「勘違いする」は「かんちがいする」と読みます。
意味は「あることを、事実とは違った様に思い込むこと」です。
「勘違いする」の言葉の使い方
「勘違いする」は動詞として「勘違いする・した」と使われます。
「勘」は「ものごとの意味やよしあしを直感的に感じとり、判断する能力」という意味、「違い」は「異なること」「誤ること」という意味、「勘違いする」で「ものごとの意味を誤って判断すること」になります。
「履き違える」との意味は、「別のものと間違えるのでなはなぃ、最初から違うものと思い込むこと」です。
「履き違える」と「勘違いする」の違い
「履き違える」は「あることの意味を、別のものと間違えること」です。
「勘違いする」は「あることを、事実とは違った様に思い込むこと」です。
「履き違える」の例文
「履き違える」の例文は以下の通りです。
・『慌てて靴を左右履き違える』
・『彼女は自由と自己中を履き違えている』
「勘違いする」の例文
「勘違いする」の例文は以下の通りです。
・『友人と妹を恋人同士だと勘違いする』
・『会議は今日だと勘違いする』
〔畑違い/お門違い〕
「畑違い」とは?
「畑違い」とは専門の分野や仕事の分野が違うことを示す言葉です。
「畑違い」は仕事以外にも学問や研究の分野や領域が違うことを表す時にも使うことが可能です。
「畑違い」はこれ以外にも兄弟姉妹の間で母親が違うことを示す意味もあります。
「畑違い」の行為や仕事は効率が悪く失敗を引き起こす可能性があり、仕事の依頼や人事異動ではこのような「畑違い」は望ましくないとされています。
「畑違い」の反対語としては「適材適所」があり、こちらは個人の能力に応じた仕事を与えて最適化することを示す言葉です。
「お門違い」とは?
「お門違い」とは間違えて家を訪問することを示す言葉です。
この言葉に使われている「お門」は御殿や皇居、一般的な住宅の門であり、「お門違い」は門の表札を見て訪問する家を間違えたことに気づくことから生まれました。
「お門違い」はこれ以外にも目当てのものと違ったことや、見当外れなこと、専門外なことを表す時にも使うことが可能です。
「畑違い」と「お門違い」の違い
「畑違い」は専門的な分野は領域が違うことを示すの時に使う言葉です。
「お門違い」は間違えて家を訪問することや見当外れなこと、目当てのものと違う時に使う言葉です。
「畑違い」の例文
・『畑違いの分野だが、アドバイスを求められました』
・『彼の研究は畑違いだが、論理的な思考方法はとても参考になりました』
「お門違い」の例文
・『責任を自分に押し付けるのはお門違いだと思います』
・『その探偵はまるでお門違いな推理を披露したので、呆れてしまった』
まとめ
「畑違い」や「お門違い」は意味が似ていることから間違えやすい言葉として有名です。
どちらも専門外のことを示す意味がありますが、「お門違い」には間違ったことや見当違いという意味でも使うことが可能です。
〔体系/形態〕
「体系」とは?
「体系」とはそれぞれ別々の要素がまとまって一つの知識や機能になっているものの全体を指します。
例えば人間の細胞についての学問や生理現象の学問や薬に対する相互反応の学問などは別々の学問ですが、それらは知識としてまとまり医学という「体系」を作っています。
このように一つの知識や機能を成り立たせるために別々のものが関連しあっているものが、どういった知識や機能によって構成されているかの全体図を指すのが「体系」です。
「形態」とは?
「形態」とは組織だった物事の全体的ななりたちやそれを構成する要素の有り様です。
例えば飲食店は調理場で料理を作り完成した料理は飲食スペースで食べさせるという業務「形態」になっています。
このようにそれぞれが機能して一つの組織体として構成していますが、飲食スペースは調理に無関係なようにそれぞれが関連し合うとは限りません。
そのため調理場での料理はそのままに飲食スペースではなくテイクアウトで提供する形に変えるなど、「形態」は都合により変化することもあります。
「体系」と「形態」の違い
「体系」と「形態」の違いを、分かりやすく解説します。
別々の知識や機能などが関連しあい一つの知識や機能を形作っているものが「体系」で、組織体を作る構成要素の有り様が「形態」です。
「体系」は全体像の基盤とも言えるもので、それぞれの構成要素が大なり小なり絡むので基本的に変化させられません。
しかし「形態」は構成要素自体の繋がりや関連性は強くないことが多く、都合や場合によって変化すられることも多いでしょう。
まとめ
構成する要素が関連しあって一つの組織体や知識になっているのが「体系」、複数要素の組み合わせでできているけれどそれらの要素が機能的に関連しあっているとは限らないのが「形態」と言えるでしょう。
また「体系」は組織のあり方や構造についての骨子や基盤に当たるので変化が難しく、「形態」はそれに比べれば変化しやすいのも違いです。
〔相当/同等〕
「相当」とは?
「相当」は「そうとう」と読み、意味は以下の通りです。
1つ目は「あるものと、価値や効果などがほぼ等しいこと」という意味です。
2つ目は「あるものごとにふさわしい度合いであること」という意味です。
3つ目は「かなりの程度であること」という意味です。
「相当」の言葉の使い方
「相当」は名詞・形容動詞として「相当だ・である」「5千円相当」などと使われます。
「相」は「外にあらわれた物の姿・様子」という意味、「当」は「あ(たる)」とも読み「あてはまる」という意味、「相当」で「外にあらわれている物の姿や様子が、他のものにあてはまること」になります。
「同等」とは?
「同等」は「どうとう」と読みます。
意味は「程度・等級などが同じであること」です。
「同等」の言葉の使い方
「同等」は名詞・形容動詞として「同等だ・である」「同等の実力」などと使われます。
「同」は「おな(じ)」とも読み、「違いがないこと」という意味、「等」は「ひと(しい)」とも読み「でこぼこがなくそろっている」という意味、「同等」で「他のものと違いがなくそろっていること」になります。
「相当」と「同等」の違い
「相当」は「外にあらわれている物の姿や様子が、他のものにあてはまること」です。
「同等」は「他のものと違いがなくそろっていること」です。
「相当」の例文
「相当」の例文は以下の通りです。
・『1万円相当の賞品が当たる』
・『収入に相当する生活を送るべきだ』
・『彼は相当努力したらしい』
「同等」の例文
「同等」の例文は以下の通りです。
・『ネイティブと同等の英会話力がある』
・『ペットを家族と同等に扱う』
・『値段は違うが品質はほぼ同等だ』
〔考えすぎる人/思慮深い人〕
「考えすぎる人」とは?
「考えすぎる人」の意味は以下の通りです。
1つ目は「本来の意味に含まれていない余計なことまで考えてしまい、やらなくてもいい言動をする性格の人」という意味です。
2つ目は、「本来の意味に含まれていない余計なことまで考えてしまい、結局気後れして行動できない性格の人」という意味です。
「考えすぎる人」の言葉の使い方
「考えすぎる人」は、日常的に使われる言葉です。
「考え」は動詞「考える」の連用形で「思いを巡らし予測・判断すること」という意味、「すぎる」は「過ぎる」と書き、接尾辞として「行為・状態などが度をこえている」という意味、「人」は「人物」という意味、「考えすぎる人」で、「思いを巡らし予測・判断することが度を超えている人物」になります。
基本的に、良くない意味で使われる言葉です。
「思慮深い人」とは?
「思慮深い人」は「しりょぶかいひと」と読みます。
意味は「ものごとについて、充分に頭の中で思い巡らす性格の人」です。
「思慮深い人」の言葉の使い方
「思慮深い人」は、日常的に使われる言葉です。
「思慮」は「充分に思い巡らすこと」という意味、「深い」接尾辞として「程度のはなはだしい様子」という意味、「人」は「人物」という意味、「思慮深い人」で「充分過ぎるほど思い巡らす人物」になります。
基本的に、良い意味で使われる言葉です。
「考えすぎる人」と「思慮深い人」の違い
「考えすぎる人」は「思いを巡らし予測・判断することが度を超えている人物のこと、良くない意味で使われる言葉」です。
「思慮深い人」は「充分過ぎるほど思い巡らす人物のこと、良い意味で使われる言葉」です。
「考えすぎる人」の例文
「考えすぎる人」の例文は以下の通りです。
・『彼女は考えすぎる人なので細かいことまで言わない方がいい』
・『彼は石橋をたたいても渡らないレベルの考えすぎる人だ』
「思慮深い人」の例文
「思慮深い人」の例文は以下の通りです。
・『彼は思慮深い人なので下手なことは言わないだろう』
・『上司は思慮深い人なので安心して判断をゆだねる』
〔襟を正す/気を引き締める〕
「襟を正す」とは?
襟を正すは、えりをただすと読むべき言葉です。
文字で記載されたこの言葉を目にすれば一目瞭然な事でしょうが、衣服の首を取り囲む部分をという意味を持つ襟をの文字に、正しくするとか整えるといった意味を有する正すの文字を加える事で成立した言葉となっています。
以上の事から襟を正すは、自分の乱れた衣服を整えるや、間違った態度を改めて気合を入れる事を示すのです。
「襟を正す」の言葉の使い方
襟を正すは、乱れた衣服や姿勢を整えるといった意味の言葉として用いられています。
ただしその意味合いから、それまでの態度を改めて気持ちを切り替えるといった意味にも使用されているのです。
「気を引き締める」とは?
気を引き締めるは、きをひきしめると読むのが正解な言葉となっています。
文字で書かれたこの言葉を見れば理解出来る事ですが、心の働きをや精神をといった意味の気をの文字に、気持ちを緊張させるとか強くしめるといった意味がある引き締めるの文字を付け足す事で成立した言葉です。
以上の事から気を引き締めるは、気合を込めるや緊張感を持って挑む事を表します。
「気を引き締める」の言葉の使い方
気を引き締めるは、気合を入れるという意味に使われる言葉です。
つまりは、油断せずに緊張感を持ちつつも事に挑むといった意味の言葉として、この気を引き締めるが駆使されています。
「襟を正す」と「気を引き締める」の違い
襟を正すと気を引き締めるの文字を見比べると、使用されている文字も読み方も大半が違っているものです。
所が厄介なのが、同じ様な意味を所有している事だったりします。
とはいえ襟を正すは、態度を改めて気持ちを込めるといった意味や、乱れた服装を整えるという意味を示すのです。
一方の気を引き締めるは、よりシンプルに、気合を入れるという意味を表します。
まとめ
2つの言葉は使われている文字も読み方も似ている訳ではありませんが、指し示す意味合いには似ている部分があるのです。
ただし襟を正すは、乱れた服装や態度を整えるという意味に加え、それまでの態度を改めて気持ちを込めるといった意味に用いられます。
対する気を引き締めるは、気合を入れるや、緊張感を持って事に挑むという意味に使われる言葉です。
〔気遣い/気を使う〕
「気遣い」とは?
仲が良い人に対して思いやる行動するのが「気遣い」【きづかい】といいます。
例えば、一緒に過ごすとき、相手を座りやすい場所に連れて行き、背もたれを置いてあげたり、膝掛けを用意するといった行動はまさに「気遣い」になるのです。
このように、相手が快適に過ごせるように考えたり、相手へ直接何があるといいか聞き、用意するその愛ある優しさを指します。
「気を使う」とは?
自分ばかりが高い評価されたとき、周囲を苛立たせないよう自慢したり、気取らず過ごすことを「気を使う」【きをつかう】といいます。
本当は他の人も上司に高い評価してもらいたかったのに、自分だけが良い思いしてはいけないと悟り、行動を慎むことこそが配慮であるわけです。
このように、相手の立場や気持ちに配慮した考え方や行動を見せる気持ちを指します。
「気遣い」と「気を使う」の違い
「気遣い」と「気を使う」の違いを、分かりやすく解説します。
相手の動きを見て、このようにすればいい状態で過ごせるだろうと考えてあげる気持ちを「気遣い」といいます。
もてなした客に物や食べ物を用意してあげたり、布団を温めてあげるその行動が気を配ることになるわけです。
また、「何か必要ですか」と聞くだけでも客に対しての「気遣い」になるわけです。
もう一方の「気を使う」は相手を手厚くもてなしたり、必要な物を渡すといった行為を指します。
「気遣い」の例文
・『家に行くと座敷に通されて、寿司を出す気遣いをしてもらった』
・『不要な気遣いをさせまいと、何も出さなくていいと伝えた』
「気を使う」の例文
・『高齢者が見舞いに来てくれたので、温かいお茶出して気を使う』
・『就職するため都会へ出る娘に父は気を使い、3か月分の生活費を渡した』
〔慣例/慣習〕
「慣例」とは?
「慣例」とは今まで繰り返しやり続けて習慣のように当たり前になっていることです。
自分がいつも決まったタイミングで決まった行動を取ることが習慣になっているように、組織や団体で決まったタイミングで決まった用事や催事を行うことが「慣例」になります。
町内会で定期的に全員参加で町の清掃をする、会社で重要な情報を共有するために毎日朝礼を開くなどがよくある例です。
それがいつ始まった習慣でどれだけ歴史があるかは問いません。
「慣習」とは?
「慣習」とは社会の中で昔から続いているしきたりです。
家庭内のような狭い範囲ではなく村に代々伝わる掟や国全体の行事などが含まれます。
例えば会社で女性はお茶くみやコピーなど簡単な仕事しか任せないと言うのは悪しき「慣習」の代表例ですし、年の初めには神社に初詣をして8月にはお盆で先祖の霊を祀るというのも「慣習」です。
その土地で生活する上で必要にかられて行われたことが続いた結果定着して「慣習」となったことも多く、「慣習」が文化として残されていることもあれば、「慣習」から法律が生まれることもあります。
「慣例」と「慣習」の違い
「慣例」と「慣習」の違いを、分かりやすく解説します。
組織や団体などで習慣として扱われている物事が「慣例」で、社会やコミュニティの中で昔から続いているしきたりやならわしが「慣習」です。
「慣例」は数年前など比較的最近始まった習慣でも問題ありませんが、「慣習」は数年前など比較的最近決まったルールなどは含みません。
まとめ
「慣例」は繰り返されていたとしても習慣でしかないので、新しくできることも廃止されることもままあります。
しかし「慣習」は長く続いていてこれはこうするべきという固定観念が強いので、急に新しくできることはないものの悪い「慣習」であっても無くすのは難しいでしょう。
〔過信/油断〕
「過信」とは?
「過信」は「かしん」と読みます。
意味は「ある人や物の価値や能力などを、実際よりも高いと思い込んで、頼りすぎること」です。
「過信」の言葉の使い方
「過信」は名詞として「過信する・した」と使われることが多くなります。
「過」は「す(ぎる)」とも読み「通りすぎる」「ある範囲や基準をこえる」という意味、「信」は「まことであると思い疑わないこと」という意味、「過信」で「価値や能力を、本来の程度以上に高いと思って疑わないこと」になります。
「油断」とは?
「油断」は「ゆだん」と読みます。
意味は「ものごとを軽んじて気を許し、注意を怠ること」です。
「油断」の言葉の使い方
「油断」は名詞として「油断する・した」「油断なく見張る」などと使われます。
語源には諸説ありますが、仏教由来の言葉という説が有力です。
仏教の経典「涅槃経(ねはんきょう)」の中に、「王が家臣に油の入った鉢を持たせて『一滴でもこぼしたら首を切る』と言った為に、家臣は必死に注意して鉢を持っていた」という物語があります。
ここから「油を断つこと=気が緩んでやるべきことを怠ること」として使われる様になりました。
「過信」と「油断」の違い
「過信」は「価値や能力を、本来の程度以上に高いと思って疑わないこと」です。
「油断」は「気が緩んでやるべきことを怠ること」です。
「過信」の例文
「過信」の例文は以下の通りです。
・『彼は自分の実力を過信している』
・『彼女は若さを過信して恥をかいた』
・『旅行でガイドブックを過信するべからず』
「油断」の例文
「油断」の例文は以下の通りです。
・『油断しているとお風呂にカビが生える』
・『油断してパスワードを人に教える』
・『産業スパイがいるので油断大敵だ』
〔一任/委託〕
「一任」と「委託」はどちらも人に頼むことを表す言葉ですが、どのような違いで区別すればいいのでしょうか。
「一任」と「委託」の違いを解説します。
「一任」とは?
「一任」とは、「物事の扱いを全てまかせること」を意味する言葉です。
「一任」の使い方
ある物事についての扱いを最初から最後まで全て他の存在に任せることを指します。
「一任」した物事については最終的な権限の執行など形式的な手続きは必要なもののどのように取り扱うか判断から最終的な結論まで全てを相手にまかせます。
一般的には任せる相手を信頼し頼る意味で用いる表現です。
自分でやらずに責任を放棄するという意味ではなく相手の能力や判断を信じて託す時に「一任」を使います。
仕事を放り出し他の人に押し付けるような場合は「人任せ」「他人任せ」などと表現して区別します。
「委託」とは?
「委託」とは、「作業や業務の一部を人に頼んで代行してもらうこと」を意味する言葉です。
「委託」の使い方
物事の取り扱いや処理を人にゆだねて託すことを表します。
一般的には処理が追いつかない業務などを本来その仕事に関わりのない存在に依頼して代わってもらうことを表す意味で使います。
法律用語として用いられている言葉ですがビジネスなどでも広く使われている一般的な言葉です。
「一任」と「委託」の違い
「一任」と「委託」の違いは「任せる範囲」です。
どちらも物事の取り扱いを他に任せることを意味する言葉ですが「一任」が全ての取扱いを任せるのに対し「委託」は一部を任せることを意味します。
「一任」は許認可などを含む広範囲な権限を託しますが「委託」は作業や実務などを任せるだけで強い権限は預けない、という違いもあります。
「一任」の例文
・『議長に一任する』
・『この件は部下に一任している』
「委託」の例文
・『業務を委託する』
・『重要な業務は外部に委託しない』
まとめ
「一任」と「委託」は任せる範囲の違いで区別されます。
行政手続きやビジネスなど重要な場面でよく使われる言葉なので違いを正しく理解しておきましょう。
〔とばっちり/八つ当たり〕
「とばっちり」とは?
「とばっちり」とは他人が引き起こした物事のせいで関係ない人が迷惑や被害を受けることです。
元々ははねて飛び散った水などを指す言葉ですが、誰かが水を飛び散らせたせいで関係ない自分が濡れてしまうことから、無関係の他人から迷惑をかけられる言葉として使われるようになりました。
「とばっちり」を受けたとしてもその原因を起こした人に悪意があるとは限らず、不注意が原因で悪意なく「とばっちり」を受けることも多々あります。
「八つ当たり」とは?
「八つ当たり」とは怒りや不満などの感情を無関係な人や物にぶつけることです。
八は数が多いことを指す言葉として使われており、怒りを抱いた原因以外の多くのものに怒りを当たり散らすことから来ています。
「八つ当たり」は意図的に誰かや何かに当たり散らしてやろうと考えそうすることもありますが、そうするつもりはなかったのに衝動的に当たってしまったこともあるでしょう。
ですがそれが意図的でも衝動的でも「八つ当たり」している時には悪意や害意から行動しています。
「とばっちり」と「八つ当たり」の違い
「とばっちり」と「八つ当たり」の違いを、分かりやすく解説します。
他人が引き起こしたことのせいで関係ない人が被害をうけるのが「とばっちり」で、怒りや不満を関係ない人にぶつけるのが「八つ当たり」です。
「とばっちり」は加害者に悪意がない場合もありますが、「八つ当たり」は衝動的なものであっても加害者の悪意や害意によって起こります。
また「とばっちり」は受動的なもので「八つ当たり」は能動的な行動です。
まとめ
無関係な被害が「とばっちり」で無関係な加害が「八つ当たり」と言えますが、「とばっちり」には悪意があるとは限らないという点は覚えておくべきです。
悪意からの行動である「八つ当たり」と違い、「とばっちり」には本人にその気がないのに被害を与えてしまったという不可抗力な場合もあります。
〔そつなくこなす/要領よく〕
「そつなくこなす」とは?
「そつなくこなす」の意味は以下の通りです。
2つ目は「手抜かりなく処理する」という意味です。
2つ目は「無駄のないように処理する」という意味です。
「そつなくこなす」の言葉の使い方
「そつなくこなす」は「そつ+なく+こなす」で成り立っています。
「そつ」は「卒」と書き、「手抜かり・手落ち」「むだ」という意味、「なく」は「無く」と書き、形容詞「ない」の連用形、「こなす」は「熟す」と書き「食べたものを消化する」から転じて「与えられた仕事などを上手く処理する」という意味、「そつなくこなす」で、与えられた仕事などを「手抜かりなく処理する」「無駄なく処理する」になります。
「要領よく」とは?
「要領よく」は「ようりょくよく」と読み、意味は以下の通りです。
「ものごとの大事な点を掴んで、無駄なく」という意味です。
2つ目は「コツを掴んでうまく手を抜いて」という意味です。
「要領よく」の言葉の使い方
「要領よく」は副詞とそして使われます。
「要領」は「ものごとの最も大事な点」「ものごとのコツやうまいやり方」という意味、「よく」は「よい」の連用形、「要領よく」で「ものごとの最も大事な点をうまく掴んで」になります。
「そつなくこなす」と「要領よく」の違い
「そつなくこなす」は「手抜かりなく処理する」「無駄なく処理する」です。
「要領よく」は「ものごとの最も大事な点をうまく掴んで」です。
「そつなくこなす」の例文
「そつなくこなす」の例文は以下の通りです。
・『彼女は秘書業務もそつなくこなす』
・『彼は家事育児をそつなくこなす』
「要領よく」の例文
「要領よく」の例文は以下の通りです。
・『彼女は職場で要領よく立ち回る』
・『データ入力を要領よく終わらせる』